広報・PR
2023.10.02
ステマとは?【広報・PRパーソン向け】10月からのステマ規制 押さえておきたいポイント
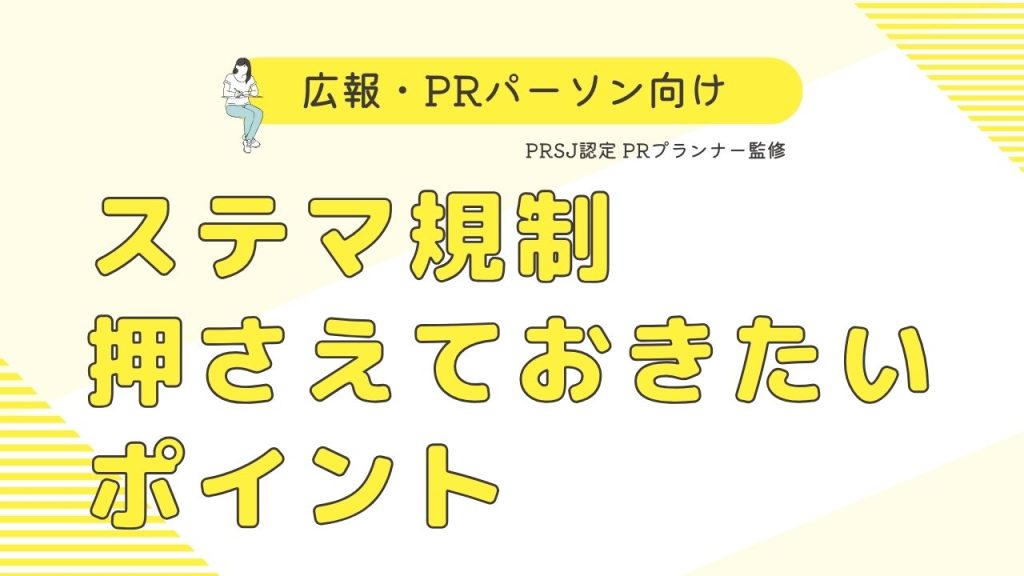
2023年10月1日から「ステマ」の規制が始まりました。「ステマ(ステルスマーケティング)」とは、広告・宣伝であるにも関わらず、それがわからないように隠してメディアに掲載したりSNSに投稿したりすること。
商品やサービスを購入する際、消費者がステマによって正しい判断ができなくなることを防ぐ目的で、景品表示法(第5条第3号)の「不当表示」として規制されることになりました。
広報・PRに携わる担当者として、知っておきたいポイントを紹介します。
対象は?
商品やサービスについての表示であれば、インターネット、SNS、口コミ、新聞、雑誌、ラジオ、TV、自社のウェブサイトなど、あらゆる文字、音声、画像、動画が対象になります。
どういうケースがステマにあたる?
商品やサービスを提供する事業者が内容の決定に関わっているのに、それを隠して表示するものがステマとされます。
インフルエンサーなどに直接的、間接的に意向に沿った口コミを依頼する、高価な商品を無料で提供した結果として良い口コミを投稿してもらうなどの場合も、その旨を明確に記載しないとステマと判断される場合があります。
規制されるのは?
今回、規制されるのは商品やサービスを提供する会社です。広告代理店やインフルエンサー、掲載したメディアではありません。
違反したらどうなる?
消費者庁から、掲載の差し止め、再発防止策の実施、違反したことの周知、今後同様のことを行わないことを求める措置命令が行われます。
いつから?
2023年10月1日から施行ですが、9月30日以前の記事や投稿でも10月1日以降にネット上に残っているものは対象になります。9月30日以前に公開された番組や紙面記事は対象外です。
ポイント① はっきりと記載する
広告、宣伝であることをわかりやすく記載することが必要です。「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」の4種類いずれかの表記が推奨されています。「A社から商品提供されています」など、文章での記載も可能です。
大量のハッシュタグの中に、「#PR」の表記を紛れ込ませる、動画の中で短い時間だけ表示する、見えづらい大きさや色で表示するなど、わかりにくい表記はNGです。
また、関係者のSNS投稿の場合、プロフィール欄に関係者である旨が記載してある程度では不十分とされ、投稿内などわかりやすい場所への記載が必要です。「関係者」は広告・宣伝に関わっているチーム、関連会社なども含まれます。
ポイント② グレーゾーンが存在することを理解する
今のところ、ステマ/ステマではないという明確な線引きがあるわけではなく、「総合的な」「客観的な」など、判断のグレーゾーンが存在します。
例えば、あるブランドのアンバサダーがそのブランドをアピールする内容をSNSに投稿した場合は、関係者であることがはっきりしているので、追加のプロモーション表記は不要です。ただし、アンバサダーであることの十分な認知がない場合には表記が必要となります。
また、事業者から依頼があっても、インフルエンサーが自主的な意思で投稿したと客観的に判断できる場合や、関係者ではあるもののプロモーションとは無関係の社員が自分の意志で投稿した場合はステマとはみなされません。この場合は「客観的に判断できる」、「無関係」であることを説明できるかどうかが判断の分かれ目となります。
一方で、明確な指示がなくても、過去に高価な商品提供があった場合や、良い口コミを投稿すれば見返りがあることを匂わせた場合など、ステマとみなされる場合があります。このように、過去も含めた関係性によって判断されます。
ポイント③ マスメディアの表示も対象になる
ステマというと、SNSや口コミサイトなどインターネットでの投稿が話題になることが多いですが、今回の規制はテレビ、ラジオ、新聞、雑誌など、マスメディアの表示も対象です。
ポイントはメディア側の「編集権」が機能しているかどうか。商品の提供や取材協力費の支払いなどがあった場合でも、正常な商習慣における取材活動の範囲内であり、編集権がメディア側にある場合はステマにはなりません。ただし、編集に対して事業者が内容を決定している場合は、タイアップ表記が必要になります。
ポイント④ 「バレなければいい」は危ない。通報先がある
消費者庁は、ステマ規制に関する情報提供の窓口を設置しています。内部通報や関係者からの相談によって、ステマであることが判明する可能性があります。関係者との情報共有や周知、不正な表記がないか確認することがリスク管理としても必要です。
景品表示法に関する情報提供・相談の受付窓口
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/
今回のステルスマーケティング規制は、商品やサービスを提供する会社が対象です。記事や、SNS投稿で自社がどのように露出してているかを把握し、関係性の不明瞭な表記がないかどうか、平時からモニターすることも大切です。
【参考資料】
「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~」(消費者庁)2023年6月作成
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf
事業者がこれから行う企画の事前相談(消費者庁表示対策課)
指導係TEL.03-3507-880
written by naigai